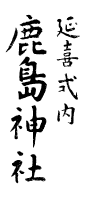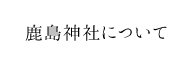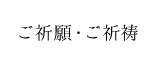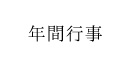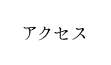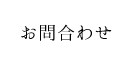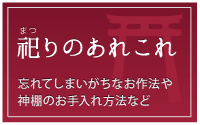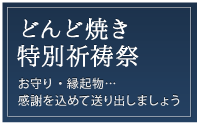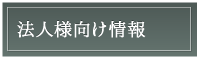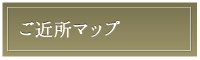長月(ながつき)…「夜長月」の略という説が有力ですが、ほかに稲刈月が転じた、あるいは長雨に由来するという説もあります。
旧暦8月15日 十五夜…一般に十五夜というのは、「中秋の名月」と呼ばれている
旧暦8月15日の月のことをさします。
中秋の名月を鑑賞する習慣は平安時代に始まりましたが、
この月見が民間に定着するにあたっては、やはりその基礎となる習俗がありました。
これが初穂祭、つまり秋の収穫祭であるとされています。
春から手をかけて育てた作物が秋には実り、人々に大事な食料をもたらして
くれます。日本人にはこの自然の恵みに感謝してこの時期いろいろなお祭りを
行いました。特にこの時期に多くお祝いされたのは里芋の収穫で、そのため、
月見に里芋を供える風習ができ、この名月を「芋名月」や「芋の子誕生」と
呼ぶ地方もあります。
9日 重陽の節句…この日は九という陽の数字(奇数)が重なることから、めでたい日とされました。
ほかに「菊の節句」とも呼ばれ、長寿の花として大切にされてきた菊の花をお供えします。
宮中では、菊の花びらを浮かべた菊酒をいただく節会(せちえ)が開かれ、民間でも被せ綿
といって前夜に菊に綿をかぶせ、九日の朝に露で湿ったその綿で体を拭いて長寿を願う行事
が行われました。
現在、家庭で特別な行事を行っているところは少なくなりましたが、各地で菊人形祭や
菊花展が開かれます。
第3月曜日 敬老の日…高齢者を敬い長寿を祝う国民の祝日。
1951年に「としよりの日」として定められ、66年に「敬老の日」と改名、祝日とされた。